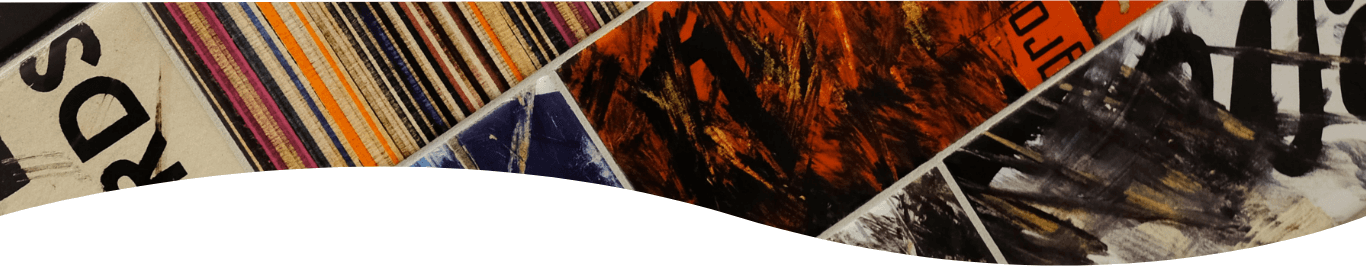
お知らせ
PADI講習で学ぶ海洋ゴミ問題と企業向けビーチクリーン提案
PADI Dive Against Debris®講習で学んだ海洋ゴミ問題から考える、企業のSDGsビーチクリーン活動のすすめ

近年、企業におけるSDGs(持続可能な開発目標)への取り組みが重要視される中、実践的で社員の環境意識を高めるレクリエーションとして「ビーチクリーン活動」が注目されています。
私ごとにはなりますが、先日、PADIが主催する国際プログラム「Dive Against Debris®」の講習を受講し、海洋ゴミ問題の現状や課題を学びました。そこで得た知見をもとに、企業のSDGs活動やCSR活動ご担当者さまに向けてのビーチクリーンの効果的な実施方法をご提案します。
Dive Against Debris®とは?


「Dive Against Debris®」は、ダイバー向けの国際的な海洋保全プログラムで、PADIと環境団体Project AWAREが連携して運営しています。
ダイバーが海中のゴミを回収し、その種類・数量・重量を記録・報告することで、世界規模のデータベースに集積。科学的根拠に基づいた海洋保護対策の推進に貢献しています。
この講習を受講することで、ただゴミを拾うだけではなく、「現状を知り、原因を理解し、持続可能な解決に繋げる」という視点が身につきます。
企業向けビーチクリーン活動のすすめ


企業がSDGsの一環としてビーチクリーンを実施する際は、単なる清掃イベントにとどまらず、以下のポイントを押さえることで、より深い学びと成果が得られます。
1. 海洋ゴミ問題の現状共有
参加者に海洋プラスチックごみの現状(例:毎年約800万トンが海に流入、海鳥の90%以上がプラスチックを摂取している)を数値で示し、問題の深刻さを理解してもらいます。
2. チームに分かれてビーチクリーン
参参加者はチームに分かれ、清掃活動を行いますが、単にゴミを拾うだけでなく、ペットボトル、プラスチック袋、漁具などゴミの種類ごとに分別しながら回収します。
この分別作業を通じて、どの種類のゴミが多いかを実感するとともに、回収後の正確な記録・分析につなげることができます。
3. ゴミの種類・数量・重量の記録
ただ拾うだけでなく、ゴミを分類・計測し記録することで、どのようなゴミが多いか、発生源の推測が可能になります。
4. 結果の共有とアクションプラン策定
集計したデータをチームで共有し、社内や個々の生活でできるゴミ削減の具体策を考えます。
期待できる効果
- 社員の環境意識向上:体験を通じてSDGsへの理解が深まります。
- チームビルディング:共同作業でコミュニケーションが活発化します。
- CSR・ブランド価値の向上:データに基づいた活動として社外に発信可能です。
SDGsレクリエーション
PADI Dive Against Debris®の講習で得た海洋ゴミ問題の知見を活かし、ビーチクリーン活動とチームビルディングを組み合わせたプログラムの企画・運営をお手伝いしております。
企業のSDGs推進において、より意義深く効果的な体験型プログラムとしておすすめです。
なお、9月から11月は気候も穏やかで海風も心地よく、ビーチクリーンを行うのに最適なシーズンです。ぜひこの時期の実施をご検討ください。







