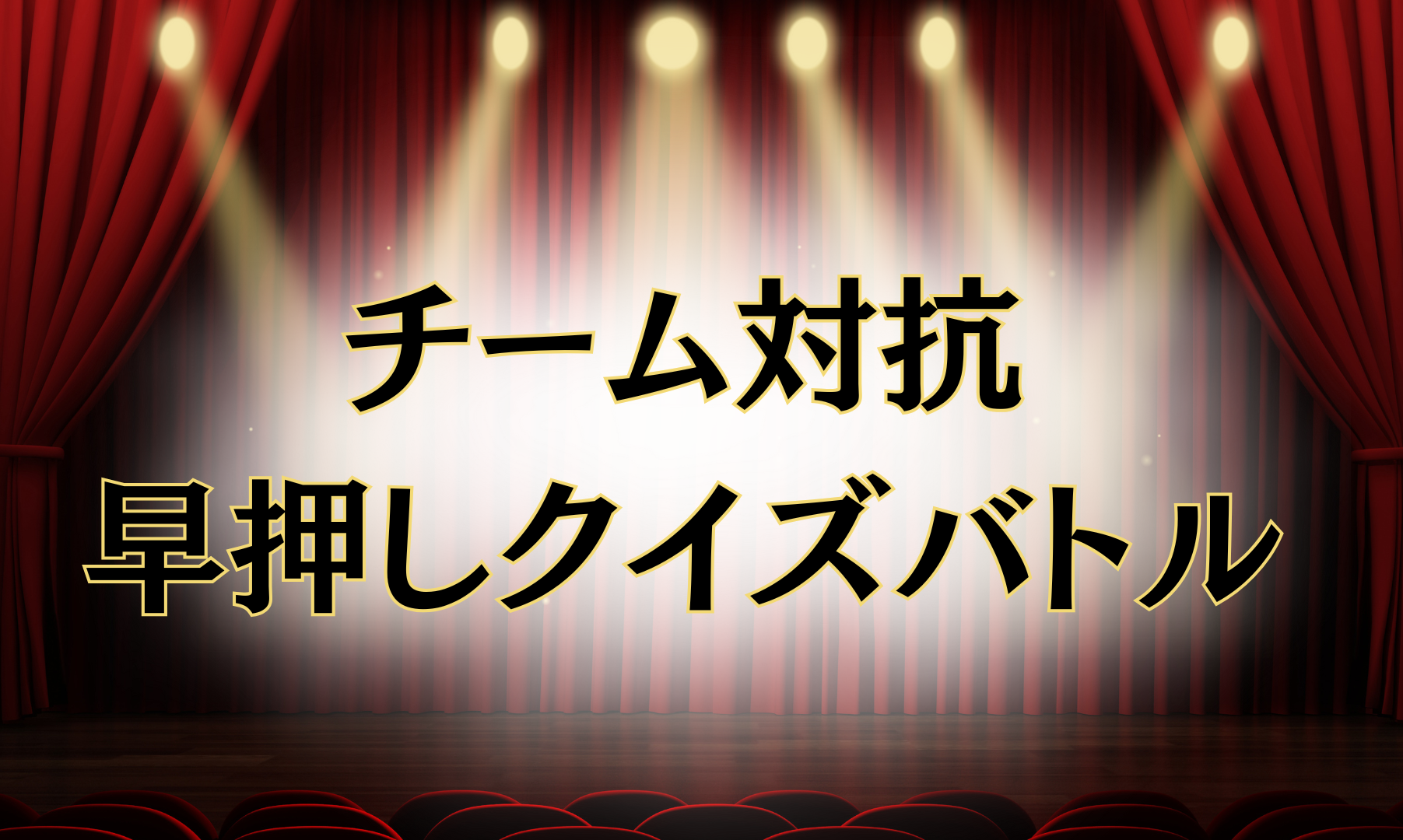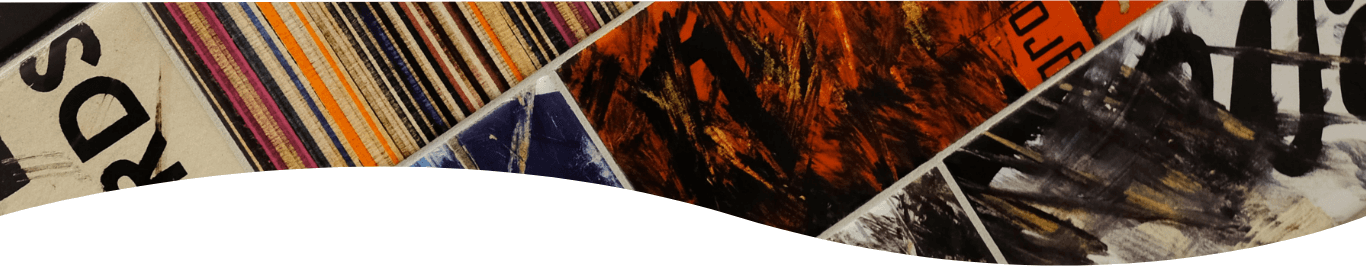
お知らせ
5月病の症状を軽減するために実践したい、チームウェルビーイング®の5つの方法
令和の時代における5月病は、単に疲れやストレスによるものではなく、職場の環境や人間関係の変化、また自己表現や仕事の意味を問い直す時期でもあります。現代の働き方や社会環境の変化、リモートワークの普及や仕事の柔軟化、情報過多変化の多い時代においては、心身の健康を維持するためにはチーム全体でウェルビーイングを意識した取り組みが必要不可欠です。
このような背景の中で、個々のメンバーが感じるストレスや不安を軽減するために、チームウェルビーイングを実践することがますます重要となっています。この記事では、5月病を軽減し、チーム全体のウェルビーイング®を高めるための5つの方法を紹介します。
1. ウェルビーイング チェックイン
チームメンバー間でのオープンで率直なコミュニケーションは、5月病を軽減するために非常に重要です。メンバーが不安やストレスを感じている場合、それを他のメンバーや上司に伝えることができる環境が整っていることが大切です。

【実践方法】
定期的な「ウェルビーイングチェックイン」を設け、個々のメンバーが感じているストレスや困難を話せる場を提供します。また、リーダーが積極的にフィードバックを行い、感謝の意を表することで、ポジティブなコミュニケーションを促進します。
チームや組織内でメンバーの心身の状態や感情を定期的に確認するための短いミーティングや質問のことを指します。目的は、個々のメンバーが感じているストレスや不安、健康状態を把握し、必要なサポートを提供することです。特に、仕事の進行状況や個々の精神的な健康をチェックすることが、ウェルビーイング(幸福感や健康)を保つためには重要です。
▶ウェルビーイングチェックインとは
この「チェックイン」は、簡単な質問を使って行われることが多いです。例えば下記のような質問です。
- ・「今、どんな気持ちですか?」
- ・「最近、仕事で困ったことはありますか?」
- ・「今日のエネルギーレベルはどれくらいですか?」
- ・「今後の目標に向けてサポートが必要なことはありますか?」

週に一度、ミーティング冒頭で「ウェルビーイングチェックイン」を行い、各メンバーが簡単に自分の気分やストレスの状況を共有する時間を設けます。このチェックインでは、メンバーが気軽に発言できるよう、リーダーや同僚が温かく受け入れる姿勢を示すことが大切です。もしメンバーが不調を感じていれば、その後にサポートを提供することができます。
これにより、自分の状態を確認し、問題があれば早期に気づき、必要なサポートを受けられるようにすることもできます。これを定期的に行うことで、チーム内での信頼関係が強まり、メンバーが孤立することなく、健全なコミュニケーションが促進されます。
2. 感謝とポジティブなフィードバックを日常的に行う
感謝の気持ちやポジティブなフィードバックを日常的に行うことが、メンバーのモチベーションとエンゲージメントを高め、5月病による倦怠感を軽減します。小さな成功や努力を認めることが、心の支えになります。

【実践方法】
チーム内で、感謝のメッセージを投稿する専用のスレッド(またはチャンネル)を作ります。このスレッドには、日々の感謝の気持ちや小さな成功をシェアしていきます。例えば、以下のようなルールや流れで進めるのもお薦めです。
▶感謝のメッセージ
- チームメンバーが、他のメンバーに感謝したことを投稿します。Slack、Microsoft Teams、Trelloなど、スレッド形式の投稿ができるツールで、専用のチャンネルやボードを作ると効果的です。
- 例:てば「○○さんがプロジェクトの進行を助けてくれて、本当に感謝しています!」などを投稿。投稿に対して、「いいね」やコメントで応援や御礼を言い合う場を作ります
- ▶ 月間感謝のトピック
- 毎月、特定のテーマやトピックを決めて、感謝のメッセージを投稿する日を設けます。例えば「今月一番感謝したこと」や「先週助けてくれた人への感謝」など、テーマに沿った感謝のメッセージを集めます。
- ▶感謝のメッセージで「ポジティブな振り返り」
- 感謝のメッセージだけでなく、その時々の小さな成功や挑戦を振り返ることで、チーム全体のポジティブな気持ちを高めることができます。例えば、あるメンバーがプロジェクトで新しいアイデアを提案してくれた場合、それを評価して感謝することは、他のメンバーにも良い影響を与えます。
- ▶定期的な「感謝振り返り」ミーティング
- 週に1回、または月に1回、チーム全員で集まり、感謝の気持ちをシェアする時間を設けます。スレッドに書き溜めたメッセージを一緒に振り返り、全員で「ありがとう」の言葉を伝え合うことで、さらに結束力が強化されます。
3. チームビルディングの活動を行う
チームビルディング活動は、メンバー同士の絆を深め、ストレスを軽減する効果があります。楽しみながら共通の目標に向かって取り組むことで、チーム全体の士気を高めることができます。

【実践方法】
弊社では、「チームウェルビーイング®」という登録商標にもとづいた、ユニークで実践的なレクリエーションを企画・運営しています。以下は、特に人気の高いプログラムの一例です
▶ゆる運動会・室内運動会
性別・年齢・体力差関係なくどなたでも楽しめる競技を中心としたゆるい運動会や、会議室内で実施が可能な「室内運動会」はチームビルディングにも健康促進にも効果的です!室内運動会ではスリッパ競争やジェスチャーゲーム、万歩計リレーなどもあります。
▶謎解きや宝探しなどのチームビルディングゲーム
メンバー同士でヒントを話し合い、知恵を絞ってミッションに挑む謎解きゲームや宝探しなどのチームビルディングゲームの実施もチームのウェルビーイングを促進するのにお薦めです。
▶格付けチェックゲーム
感性&知識を頼りに、チームで格付け勝負!高級食品を当てたり、音の違いを聞き分けたりと、笑って盛り上がれるエンタメ型のプログラム。チーム戦でも実施もOK!
▶oVice懇親会
特に、リモートワークが多い場合、バーチャルで参加できるチームイベントを企画するもの効果的です。oViceイベントについては【こちら】を御覧ください。
4. ネイチャーチームビルディングを取り入れる
5月の爽やかな気候を活かして、自然の中で行うチームビルディングは、心身のリフレッシュとチームの結束力を高める素晴らしい方法です。アウトドア活動は、ストレスを軽減し、チームメンバー間の信頼を深める効果があります。

ネイチャーチームビルディングは、自然観察を通じて、環境保護や生態系の理解を深めながら、チームの協力精神を育むプログラムです。一人では気が付かないこともチームでの自然観察を通じて新しい発見が生まれます。生物や植物の名前を覚えることが目的ではなく自然の中での気づきや、チームビルディング、SDGsへの意識向上を大切にしたレクリエーションです。
【実践方法】
自然の中でのゲームを通じて自然保護の意識を高め、チームビルディングを促進します。ゲームの一例をご紹介します
▶カラーハントゲーム
チームごとに自然の中から指定された色の葉や植物を探し、見つけたアイテムを写真で提出。自然の中には、目に見えにくい色や微細な色合いがたくさんあります。よく見ないと見逃してしまいます。1人では見つけられなくてもチームで協力することにより、見えてくる色・生物・植物があります。多くの動植物が異なる環境や色合いで共存しており、これらはすべてがバランスを保つために重要な要素です。このゲーム通じて、生物多様性についても理解が深まります。
▶フィールド宝探し
指定された「宝」を探し出すゲーム。宝は自然のものを使います。木の実、葉っぱ、花などの指定されたお題(宝)を、チームメンバーが協力して探し出し、どのような環境や生態系の中に存在するのかを理解することが目的です。。
5.環境や社会に貢献できるアクティビティをチームで体験する
5月は気候も穏やかで、自然の中で過ごすには最適な季節です。そんな時期だからこそ、「楽しさ」と「社会的意義」を両立したアクティビティをチームで体験することが、心とチームに深い充実感をもたらします。

弊社では、チームウェルビーイング®の考え方に基づき、SDGsをテーマにしたレクリエーションの企画・運営も行っています。自然体験や社会課題にチームで向き合うレクを通じて、個々のウェルビーイングンの促進も促します
【実践方法】
例えば、弊社が提供するチームウェルビーイング®レクリエーションの中でも特に人気なのが、**SDGsの視点を取り入れた「アップサイクルワークショップ」や「ビーチクリーン活動」**です。
▶ビーチクリーン活動やマイクロプラスチック採取体験
チームでゴミ拾いに取り組むことで、環境への意識が高まるだけでなく、「人のため・社会のために行動する」経験が自己効力感やチームとしての誇りへとつながります。
▶アップサイクルワークショップ



マイクロプラスチックや海洋ゴミ、廃材や使用済み素材を活かして、チームでアートや実用品を制作します。物を大切にする意識を育みながら、「一緒に創り上げる」プロセスを通じて、自然と対話や協力が生まれます。
こういったSDGsアクティビティは、チームウェルビーイング®の構成要素でもある「つながり」「意味」「貢献」を同時に育む、非常に効果的な実践例です。
5月病をきっかけに、チームの“健やかさ”を見直すチャンスに
連休明けのゆらぎやすい時期こそ、メンバー同士のつながりを深め、チームとしての安心感や目的意識を育てることが大切です。今回ご紹介したような、小さな工夫やレクリエーションの機会を通じて、チーム全体のウェルビーイングは確実に高まっていきます。
弊社では、「チームウェルビーイング®」をテーマに、五感を使って心身を整える体験型レクリエーションを企画・運営しております。ネイチャー体験、室内レク、リモート開催、SDGsを取り入れたプログラムなど、目的に応じたプランをご提案できますので、ぜひお気軽にご相談ください。